虫歯は全身疾患です
虫歯は「お口の病気」だけではなく「全身の病気」です。虫歯は多くの人が抱える問題ですが、「甘いものを食べただけで本当に虫歯になるの?」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。
以前のコラムでも触れたかもしれませんが、今回はアメリカのロマリンダ大学のラルフ・スタインマン博士とジョン・レオノーラ博士の研究をもとに、少し違った視点からお話ししてみます。
実は、歯も骨や筋肉と同じように「生きた組織」です。健康な状態を保つためには、毎日栄養をしっかり取り入れる必要があるのです。そしてその栄養の循環には、【DFT(象牙質液圧:歯の中の液体の流れ)】が深く関係しています。
スタインマン博士は、放射性物質(アクリフラビン塩酸塩)を健康なラットに注射して、体内の液体の流れを調べました。その結果、栄養状態の良いラットでは、血液を通して栄養が歯の内側にある「歯髄(しずい)」に届き、象牙質の中の細い管(象牙細管)を通ってエナメル質に達し、最終的に口の中に排出されていることが分かりました。
しかし、虫歯を起こしやすい食事(砂糖や精製された炭水化物など)を与えると、この流れが逆転してしまったのです。つまり、口の中の液体が外から歯の中に入り込むようになり、細菌や汚れも一緒に歯の奥まで侵入してしまう。こうして虫歯がどんどんできてしまいました。
この流れは、食事を変えることでコントロール可能だったというのが、非常に興味深いポイントです。ラットが口を使わず胃に直接食べ物を入れた場合でも、同じ結果が得られました。つまり、「何を食べるか」が虫歯の原因に大きく関わっていたのです。
鍵になるのは、耳の下にある「耳下腺(じかせん)」から分泌されるホルモンです。このホルモンが正常に働くと、歯の中から外に向かって液体が流れ、歯の表面まで栄養を運んでくれます。ところが、ホルモンの働きを弱めてしまう食事(特に砂糖や加工食品など)を続けると、この流れが止まり、虫歯ができやすくなります。
ちなみに、実験に使われたラットは歯を一切磨いていませんでした。それでも、歯に触れないように食事を与えても虫歯になったという結果が出ています。歯磨きは大切ですが、それだけでは虫歯を防げないということも分かります。
また、高炭水化物の食事に加えて、抗酸化物質(体のサビを防ぐ栄養素)が不足すると、歯の内側にある液体の流れが乱れ、細菌が歯の中に入り込みやすくなります。ビタミンA、C、D、E、K、セレン、ヨウ素などを含む食事は、歯の健康を保つ上でとても大切です。
もちろん、歯の汚れ(プラーク)や口の中の細菌、唾液の質や量、食事のタイミングや内容など、虫歯に関係する要因は他にもたくさんあります。そして、これらの影響は象牙質液圧(DFT)が低下していると、さらに大きくなります。
つまり、歯を磨くことはもちろん大事ですが、それだけでは足りないということです。日々の食事や栄養バランスが、虫歯を防ぐためにはとても重要なのです。
皆さんはどう思われますか?
≪参考文献≫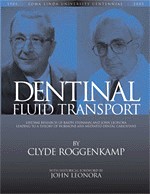
 HOME
HOME 診療内容
診療内容